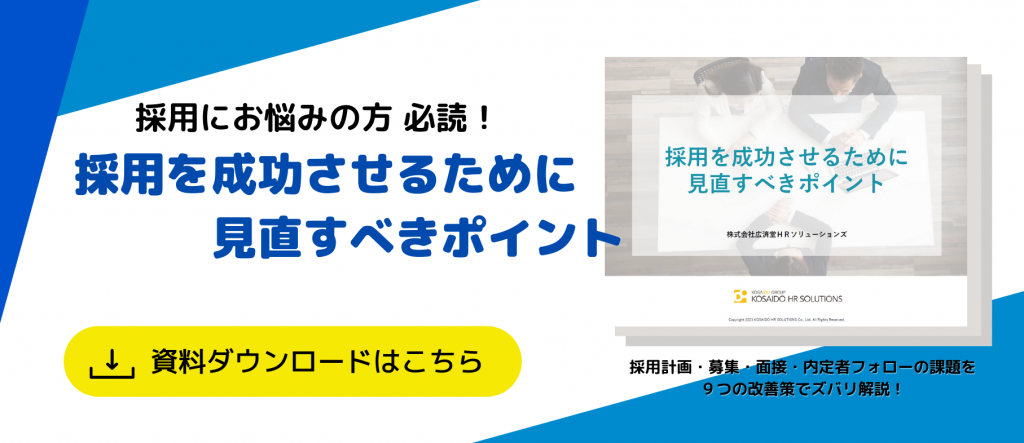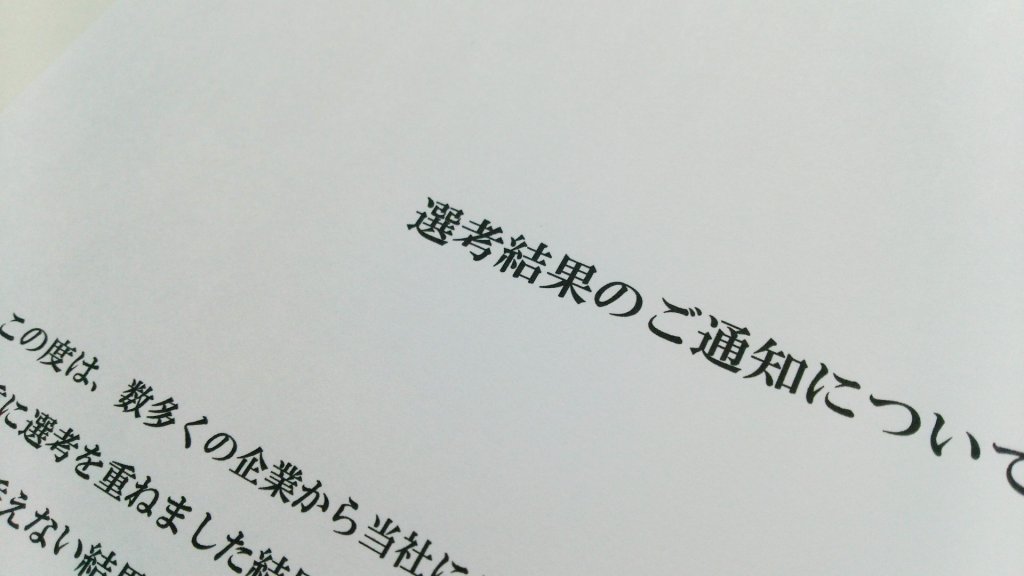
【送りにくい不採用通知メール】作成のポイントと注意点を紹介
求人募集を行い、面接を行ったものの採用にいたらなかった場合、応募者に不採用の通知が必要になります。しかし、不採用通知というのは、送るほうも受け取るほうも気が重くなるものです。
受け取った相手をなるべく不快にさせないためには、どのような内容が適切であるか、悩む採用担当者の方も多いのではないでしょうか。
今回は、不採用通知メールの作成ポイントと注意点を解説します。メールの例文も、あわせて紹介します。不採用通知の内容で悩んでいる採用担当者の方は、ぜひご覧ください。
この記事の目次
【メール例文】不採用通知の書き方
ここでは、不採用通知の例文を3つ紹介します。下記を参考にテンプレートを作成し、状況に応じて編集して活用ください。
例文1
件名 【採用結果のご連絡】|〇〇株式会社
○○ ○○様(フルネーム)
〇〇株式会社採用担当の××と申します。
この度は多数の企業から弊社にご応募いただき、誠にありがとうございました。
ご応募いただいた書類について厳正なる選考を行った結果、
誠に残念ではございますが、今回は採用を見送らせていただくこととなりました。
せっかくご応募いただいたにもかかわらず、ご期待に沿えず申し訳ございません。
なお、応募書類につきましては、弊社にて責任を持って破棄させていただきます。
○○様の今後のご活躍とご健勝を心よりお祈り申し上げます。
例文2
件名 【採用結果のご連絡】|〇〇株式会社
○○ ○○様(フルネーム)
〇〇株式会社採用担当の××と申します。
この度は数ある企業から弊社にご応募いただき、誠にありがとうございました。
さて、書類選考の結果についてですが、
厳正なる選考の結果、誠に残念ながら今回はご希望に添いかねる結果となりました。
ご期待に沿えず、大変申し訳ございません。
なお、応募書類につきましては、後日履歴書に記載されておりますご住所に
郵送にて返却させていただきます。
○○様の一層のご活躍とご健勝を心よりお祈り申し上げます。
例文3
件名 【採用結果のご連絡】|〇〇株式会社
○○ ○○様(フルネーム)
〇〇株式会社採用担当の××と申します。
この度は数ある企業から弊社にご応募いただき、誠にありがとうございました。
また、先日は弊社までご足労いただいたこと、重ねてお礼申し上げます。
さっそくではございますが、選考の結果をお伝えいたします。
面接でお伺いした内容を踏まえ、社内にて厳正なる選考を行った結果、
誠に残念ではございますが、今回は採用を見送らせていただくこととなりました。
ご期待に沿えず、誠に申し訳ございません。
応募書類につきましては、弊社にて責任を持って破棄いたしますので、
ご了承くださいますようお願い申し上げます。
○○様の今後のご活躍とご健勝を心よりお祈り申し上げます。
応募者のことを考えた不採用通知のポイント
不採用の通知を送る際、採用にはいたらなかったとはいえ、応募者は自社を選んで応募してくれた人です。今後の関係性も考えて、応募者のことを考えた対応を心がけましょう。
不採用通知メールを送るときに、意識すると良いポイントを解説します。
件名はわかりやすく
不採用通知メールでまず重要なことが、件名をわかりやすくすることです。応募者が記載しているメールアドレスには、自社のメール以外にも、ほかの企業の合否メールなども含めて、さまざまなメールが届きます。
多くのメールに紛れてしまわないように、件名は「【採用結果のご連絡】|〇〇株式会社」など、わかりやすくシンプルにしましょう。
宛名はフルネームで明記
宛名はフルネームで明記するようにしましょう。「貴殿」などと記載すると、テンプレートを使って事務的に対応されたと捉えられやすいからです。また、氏名も個人情報であるため、誤って別の人に送らないようチェックを徹底しましょう。
挨拶と謝意は忘れない
応募者との関係は、書類選考や面接が終われば終了とは限りません。応募者が自社サービスや商品の利用者になったり、取引先企業に入社したりすることも考えられます。
不採用通知メールといえど、会社を代表して送っているものです。会社の印象が損なわれないように、挨拶と謝意を忘れないようにすることも大切です。
不採用通知の場合は時候のあいさつは不要ですが、自社に興味を示して応募までしてくれたことに対して感謝を伝える文章も盛り込んでおきましょう。
選考結果は端的に
「不採用です」と直接的な文章にすると不快に感じられますが、遠回しになりすぎても何が言いたいのかがわからなくなります。
分かりやすい例として、「採用を見送らせていただくことになりました」「ご期待に添いかねる結果となりました」など、選考結果は端的に伝えましょう。
応募書類の取り扱い方も明記
応募書類は応募者の氏名や住所、電話番号といった個人情報が詰まっています。不採用になった場合に、どう扱われるのか不安に感じる人も多いため、応募書類の取り扱いについても記載しておくと親切です。
郵送で返却する企業もありますが、応募者が多いと担当者の負担が重くなります。返却が難しい場合は、「弊社で責任を持って破棄する」などと記載しておくと良いでしょう。
不採用通知メールを送る際の注意点
メールの内容以外にも、不採用通知メールを送る際に、注意したいことがあります。不採用者にも、最後までしっかりと対応する考え方を持つことで、会社の価値を高めます。
候補者には全員通知を送る
企業によっては採用業務効率化のために、採用者のみ連絡としているケースもあります。しかし、採用、不採用にかかわらず全員に通知をしたほうが、応募者が「丁寧な対応をしてもらえた」と良い印象を抱きます。
応募者が多く対応が難しい場合は、少なくとも面談や面接まで進んだ人だけでも、通知を送りましょう。
合否がわかり次第迅速に対応する
書類送付や面接から何日も待たされると、応募者が不安を感じます。合否が決まってからできれば3日以内、遅くても1週間以内には通知を出しましょう。
時間がかかる場合や伝えた期日に間に合わない場合は、あらかじめその旨を連絡し、応募者を待たせすぎないことが重要です。
不採用理由を問われたら配慮を忘れない
不採用通知には、不採用の理由を記載する必要はありません。しかし、不採用になったことに納得できない、今後のために理由を知りたいといった理由で応募者から問い合わせが入ることもあります。
このようなときには、不採用に至った詳細は伝えられなくても、真摯に向き合った姿勢を見せることが大切です。
連絡先のチェックを怠らない
不採用通知を送るときには、連絡先の確認を徹底しましょう。連絡先のチェックを怠ると、採用者に不採用通知を送ってしまうことや、同じ人に2度も不採用通知を送るといったトラブルが発生することもあり得ます。
また、送付先を誤ると、応募者の氏名や合否といった個人情報の流出につながります。送付先をダブルチェックするなど、「採用フローを明確にする」「連絡先の管理を厳重にする」ことが重要です。
応募者管理や採用、不採用通知の送付がスムーズに進まないと悩んでいる企業や採用担当者の方は、ぜひTalentClip(タレントクリップ)の導入をご検討ください。
TalentClipは、応募者対応や面接選考、内定者フォローまで、採用業務を一括管理できる採用管理システムです。
応募者の情報を細かく管理できるため、合否が決まり次第速やかに、かつミスがないように通知を送付するのに役立ちます。詳細は下記よりお問い合わせください。
下記より採用業務で役立つ資料もダウンロードできます。
まとめ
不採用通知メールは、担当者にとっても応募者にとっても気分が重くなるものです。また、企業のイメージを左右するものでもあるため、応募者に不快感を抱かせないように、文章や送るタイミングに配慮しましょう。
事務的な対応は避けるのが賢明ですが、担当者の負担が重くなりすぎないように、テンプレートを用意しておくのがおすすめです。今回紹介した内容を参考にして、さっそくテンプレートづくりに挑戦してみましょう。