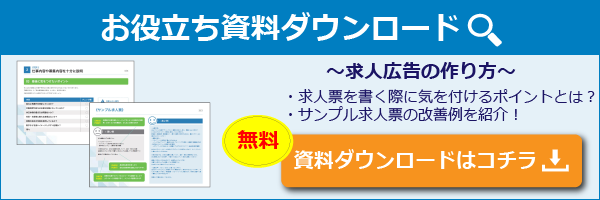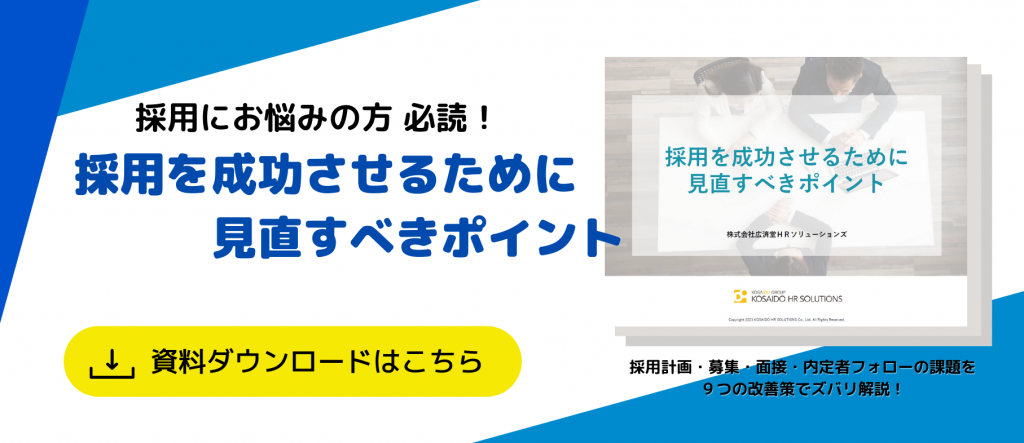自社に合った求人広告とは?求人広告の特徴を種類別に紹介
求人広告とは、企業が従業員を募集するために掲載する広告のことをいいます。採用活動においてどの求人広告を選ぶかは、応募者層や人数に関わる重要な要素です。
この記事では、求人広告にはどのような種類があるか、どのように選べば良いかを解説します。
この記事の目次
特定の層にアプローチできる!紙媒体の求人広告
紙媒体の求人広告の特徴は、地域別に求職者にアプローチできることです。特定の紙媒体を手に取ることが多い年齢層をねらってアプローチを図ることもできます。
また、紙媒体の求人広告は、単なる求人広告としてだけでなく、会社自体の宣伝効果が見込めるのも特徴です。特に、地域に特化したビジネスを展開している会社、地域に根差した会社には活用するメリットがあります。
一方、紙媒体は掲載できるスペースが限られているため、多くの情報を提供できるわけではありません。情報を絞って掲載することになるため、求職者にとって必要な情報を盛り込めない、伝えたい情報をすべて伝えきれない、などのデメリットもあります。
さらに、一度発行すると変更や修正もできませんし、掲載期間中の取り下げも不可です。このため、採用活動が終了したにも関わらず、問い合わせを受けることもあります。
紙媒体の中で代表的なのは、フリーペーパー(求人情報誌)、新聞の折り込みチラシが挙げられます。それぞれの詳しい特徴を紹介します。
フリーペーパー(求人情報誌)
フリーペーパー(求人情報誌)は、求人情報を集めた紙媒体の求人広告です。ほとんどは周辺エリアの求人情報となっており、求職者の生活圏内、たとえばコンビニや駅などに多く設置されています。
無料なので気軽に手に取ってもらいやすいのが特徴です。インターネットに不慣れな高齢者層などへ訴求したいときに効果的な求人広告といえます。
新聞の折り込みチラシ
新聞の折り込みチラシとして求人広告を出す方法もあります。折り込みチラシは、配達日、配達できる地域を指定して配布できるので、ターゲット層がいれば訴求効果も高いでしょう。
新聞を取っている層で職を探している、たとえば高齢者層や主婦層などをターゲットにする際に向いています。正社員募集だけでなく、パートやバイトで募集をかけたいときにも向いている方法です。
手軽に情報発信できるのが魅力的!Web媒体の求人広告
Web媒体の求人広告の特徴は、インターネットでより多くの人に、素早く求人情報を届けられることです。エリアも局所的にならず、全国の転職希望者を含め、幅広い層に求人情報を見てもらえる可能性があります。
業界別など、項目に特化した専用の媒体もあるため、採用ニーズに合わせて、母集団の多い媒体を選択したり、専門に特化した媒体を選択したりと、媒体を選べるのも特徴です。
さらに、紙媒体と比べると、Web媒体は、より多くの情報を伝えられるメリットもあります。文字情報に加え、写真や動画の掲載も可能です。職場の風景や仕事の様子など、文字だけでは伝わりにくい雰囲気を伝えることもできます。
ただし、Web媒体は、『掲載課金型(掲載することで料金が発生する体系)』、『成果報酬型(採用が決定すると料金が発生する体系)』など、媒体で課金体系が大きく異なる点に注意しなければなりません。
確認を怠ると予想以上にコストがかかることもありますので、利用前に、課金体系はよく確認しておきましょう。
以下、Web媒体の求人広告の種類である、求人サイト、採用サイト、求人検索エンジン、SNSについて紹介します。
求人サイト
求人サイトは、就職や転職などの求人情報を掲載している求人広告会社のサイトです。
Web媒体の求人広告の中でもよく活用されていて、求人サイトによってさまざまな人の流入を期待できます。
特にインターネットを利用する機会の多い若年層をターゲットとした採用に効果的です。
紙媒体と比べると求人情報をより細かく掲載できるため、求職者に訴求しやすくなるのが特徴です。また、自社サイトに誘導してより詳しく会社の魅力を知ってもらうこともできます。
採用サイト
採用サイトは、自社のホームページに採用のためのページを作成して求人広告を載せる方法です。自社のホームページ内に専用ページを作るため、掲載費用が発生することはありません。
外部に委託する場合には作成費用がかかりますが、ランニングコストがかからないため、コストを抑えられる点が特徴のひとつとしてあげられます。
また、採用サイトは掲載文字数や写真数などに大きな制限がなく、柔軟に作成できるため、自社の魅力を余すことなく発信できるのが特徴です。より深い情報、求職者のためになる情報を知ってもらうには採用サイトが活躍するでしょう。
求人検索エンジン
求人検索エンジンは、さまざまな求人サイト、採用サイトから求人情報を集めたものです。利用者は求人検索エンジン内で検索することで複数の求人サイトから同時に求人情報を取得できます。
代表的な求人検索エンジンは、IndeedやGoogleしごと検索です。クリック数に応じて課金されるなど成果型報酬のサービスなどもありますが、掲載自体は無料で行えることがほとんどです。コストを抑えつつ、求人を掲載できるでしょう。
SNS
SNSによる求人広告は、TwitterやFacebookなどのSNSを利用して求人広告を掲載する手法です。SNSで直接採用するのではなく、掲載した求人広告から、自社の採用サイト、または掲載している求人サイトの自社ページに誘導する方法が一般的です。
特徴は、求職者との距離が近いこと。求職者とのコンタクトがとりやすいため、求職者は応募前に不安を解消することができ、お互いにミスマッチを回避できます。
さらに、SNSの特徴であるフォロワー数、リアクション数などを活用してうまく運用すれば、企業のブランディングも可能です。特にSNSを利用している層に対して、企業のイメージを印象付けたり、求人における企業の価値を高めたりすることができます。
求人広告以外の媒体も!人材獲得につながる3つの手法
求人広告以外でも、人材獲得につながる媒体はあります。代表的なのは、ハローワーク、人材紹介、合同説明会です。
ハローワーク
ハローワークは、厚生労働省の管理する職業紹介サービスです。公共職業安定所ともいわれます。公的な事業のため、求人情報を無料掲載できるのが特徴です。
コストをかけずに求人情報を掲載できるため、多くの企業が利用しています。ハローワーク経由の採用で助成金が下りることもあるため、助成金の利用を考えるなら、併用して利用したいサービスです。
ただし、求人広告とは異なり、掲載内容が決まっているため情報は限られます。求人広告のように、さまざまな情報を盛り込めません。
そのため、ハローワークでの求人掲載だけでは、ターゲット層に刺さらないこともあります。また、多くの企業が情報を掲載しているため、応募が来たとしても、即戦力の採用や早期の採用にはあまり向いていません。
ハローワーク単体で取り入れるのではなく、求人広告との組み合わせで考えることをおすすめします。
人材紹介
人材紹介は、人材紹介会社に登録している人材の中から、自社の採用要件に合った求職者をエージェントに紹介してもらうサービスです。サーチ型ともいって、エージェントはさまざまな手段で人材を探し、ヘッドハンティングをして人材を紹介します。
人材紹介の特徴は、求職者の志向性などを考慮して人材が紹介されるため、マッチング率が高い傾向にあることです。また、自社で募集を行わず人材を紹介してもらえるため、採用活動の工数削減にもつながります。
一方で、人材紹介は採用単価が高くなりやすいのが注意点です。人材紹介ばかりに頼ってしまうと、通常の採用活動よりも多額のコストが発生することもあります。
人材紹介を利用するなら、どのくらいの割合で利用するか、どのような人材の採用に利用するかなども検討しておくと良いでしょう。
合同説明会
多くの求職者が集まる合同説明会に参加する方法もあります。合同説明会は、全業種を対象にしたもの、業界に特化したもの、学生向けなら学部などに特化したものなどがありますので、欲しい人材やアピールしたい層に合わせて参加可能です。
合同説明会に参加するメリットは、自社のことを知らない層、あまり興味のなかった層に対しても、直接的に自社の魅力をアピールできることでしょう。合同説明会をきっかけに興味をもってもらえることもあります。
世間的にあまり認知されていない会社、スタートアップで認知度の低い会社などにとっては、アピールする絶好の機会となるので、検討してみるのも良いでしょう。
なお、合同説明会は規模やエリアなどで参加費が大きく変わりますので、参加費含めてよく検討されることをおすすめします。
欲しい人材はどこで見つける?求人広告の選び方
ここまで紹介したように、求人広告にはさまざまな種類があります。多様な求人広告の中から自社に合った求人広告を見つけるにはどうすれば良いのでしょうか。
求人広告選びで意識したいふたつのポイントを紹介します。
採用ターゲットを軸に選ぶ
利用する求人広告によって、訴求しやすい層は変わります。とにかく掲載するのでは効果的な訴求は見込めないため、まずはどのような人物を採用したいのか、人物像を明らかにしておきましょう。
採用ターゲットとなる人物像を明確にすることで、どのような求人広告を利用するべきかの目安になります。求人広告を選択する際は、採用ターゲットが利用している可能性が高いものを選ぶようにしましょう。
掲載にかかるコストだけで考えず、費用対効果の高い求人広告を選ぶのがポイントです。
複数の求人広告を同時に利用する
求人広告にはさまざまなものがあると説明しましたが、利用する求人広告をひとつに絞る必要はありません。
人材を求める企業は多いため、ひとつだけに絞るとほかの求人で埋もれる可能性がありますし、思うように応募者を集められない可能性もあるためです。
コストの面も考慮しつつ、求職者の窓口を広げられるように、採用ターゲット層に訴求できる求人広告を複数利用するのが人材集めのコツです。ターゲットにリーチできるような求人広告は組み合わせて活用し、人材確保を強化しましょう。
ただし、あまりにも利用する求人広告が多いと管理しきれなくなります。求人情報が古いままだと求職者に不信感や不安を抱かせるかもしれません。
求人広告を複数組み合わせる場合は管理体制を整えると同時に、管理できる範囲で利用するようにしましょう。
採用管理システムのTalentClip(タレントクリップ)なら、求人広告を簡単に掲載できる機能が搭載されています。
テンプレートを利用した求人票作成や採用サイトの作成、求人メディアWorkinやIndeed、Googleしごと検索との連携も可能です。さらに、作成した求人票はそのまま自動掲載できるため、媒体探しの手間も省けます。
また、効果的な求人広告の書き方については、以下の資料で詳しく紹介しています。
まとめ
求人広告は、大きく分けて紙媒体とWeb媒体があり、さまざまな特徴を有しています。
求人広告選びで重要なのは、自社の採用ターゲットにマッチした求人広告を選択することです。採用ターゲットに訴求できる求人広告を効果的に利用して、求職者にしっかりアプローチできるようにしましょう。