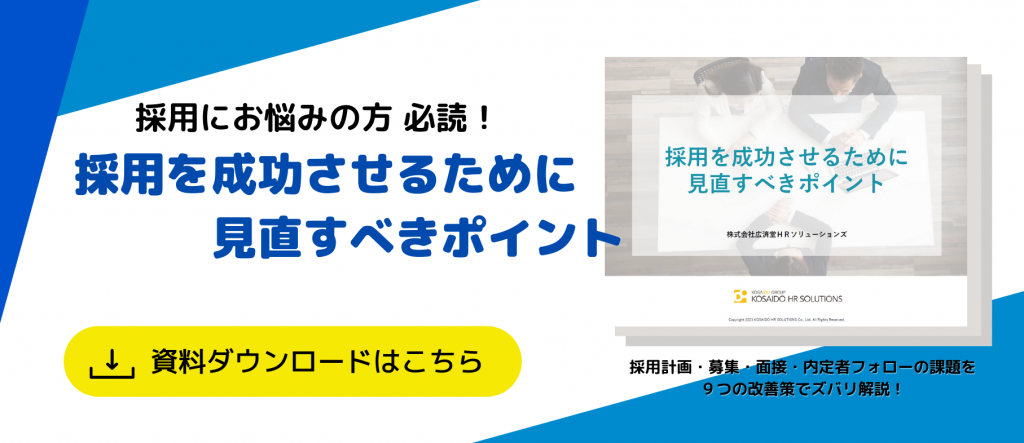【フレームワークあり】採用戦略を立てる4つのステップと重要性
思うように優秀な人材を確保できないと悩みを抱える、採用担当者の方は多いのではないでしょうか。採用活動がうまくいかないなら、採用戦略の見直しを考える時期なのかもしれません。この記事では、採用戦略の重要性から立て方、採用戦略で利用できるフレームワークを紹介します。
この記事の目次
採用戦略とはどんなものか?
まず、採用戦略とは何か改めて整理してみましょう。
採用活動の方針となるもの
採用戦略とは、簡単に説明すると採用活動の指針となるものです。
待っていれば人材が集まるという時代もありましたが、労働生産人口の減少などによる人材不足、売り手市場への変化により、人材の獲得は難しくなってきています。ただ待っているだけという採用スタイルでは、思うように人材を確保できない時代になっているのです。
このような状況の中で、自社にとって的確、かつ効果的な採用戦略を練ることが重視されるようになってきました。
採用のステップを踏んで戦略を実行に移していくことで、採用活動の無駄や同じ失敗を防ぐことができるためです。採用戦略を立てることは、主に採用業務を均質化すること、安定した人材の確保が可能になることにも期待がもてます。
採用戦略が重要視される理由
採用予定人数が少ない中小企業の場合は、採用戦略の必要性を実感しにくいのではないでしょうか。
優秀な人材を効率良く採用したいのであれば、企業規模に関係なく採用戦略は重要です。採用戦略を立てることが重要視される理由は、次の3つがあげられます。
母集団を形成するため
採用戦略を立てて効率的な採用活動を行わなければ、そもそも応募者が集まらず、採用計画に支障が生じるおそれがあります。たとえば採用戦略の中には自社が求める人材をターゲットとして設定することも含まれるため、きちんと明確にしておかなくてはアプローチ方法が絞り込めません。
ターゲットが不明瞭なままで採用活動を行えば、欲しい人材の興味をひく採用サイト作りや、人材が集まりやすい媒体への求人広告掲載ができず、応募者不足となります。仮に求める人材に求人広告を見てもらえたとしても、採用条件が伝わりにくければ応募には至りません。
採用戦略を立ててピンポイントで採用活動を行うことは、応募者を集めて母集団を形成することにつながります。
母集団形成については、以下のページでも詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
あわせて読みたい ☞
人事担当者必見!採用活動を円滑にする【母集団形成】のポイント
選考中・内定後の辞退率を下げるため
採用戦略は、応募者が辞退するリスクを下げるためにも重要です。自社としては採用するつもりでも、選考中や内定後に求職者側の意思で辞退されてしまうことがあります。
求職者が選考中や内定後に辞退する理由は、主に「企業へ不信感を抱いたから」「他社からの内定が出たから」です。
求職者の多くは、複数の企業に並行して応募しています。なかには自社より待遇の良い企業やレスポンスの早い企業も含まれる可能性が高く、採用戦略があいまいな状態での対応では、選ばれる確率は低くなるでしょう。
採用戦略が明確ではなく、選考がスムーズに行われないと、求職者はさまざまな場面で会社に対して不信感を抱きます。レスポンスが遅かったり、質問への答えが担当者ごとに変わったりする選考では、他社からの内定が出た時点で自社のほうが選択肢から外されてしまいます。
このような事態を避けるためには、あらかじめ採用戦略を立てたうえで明確なターゲット像、採用フローを作り込んでおく対策が必要です。
入社後のミスマッチを防ぐため
スムーズに採用、入社に至ったとしても、ミスマッチを感じれば早期離職のリスクが生じます。ミスマッチは求職者だけではなく、企業側にも起こるものです。
・求職者側:「社風が合わない」、「仕事内容がイメージと違った」など
・企業側:「採用した人物と求めるスキルが合わない」など
早期離職が起これば、再び採用活動を行うために、あらゆる媒体へ求人票を提出したり応募者に対応したりと、採用コストがかかります。何度も早期離職が繰り返されると、その分余計にかかる採用コストは多くなるため、選考の早い段階でミスマッチのリスクを軽減させる必要があるのです。
採用戦略で重要となる要素
採用戦略を立てるときに、マーケティングの要素を取り入れる企業も増えてきました。マーケティングのフレームワークを使って採用戦略を立てることを、採用マーケティングといいます。
採用マーケティングとは、企業側の視点ではなく、求職者の視点に立ってさまざまな活動を整理し、採用を計画していくことです。採用マーケティングでは、求職者を通常のマーケティングの顧客と位置付けます。
このように、採用マーケティングが注目されるようになったのは、ターゲットになる求職者の情報を集めて分析することが、効率の良い採用活動につながるためです。永続的な母集団の形成、求職者データの蓄積が、採用マーケティングの精度を高めるとされています。
一般的に、消費者が商品を認識して購買するまでの心理をカスタマージャーニーといいます。採用活動におけるカスタマージャーニーは、企業を認識して内定や採用に至るまでの心の動きです。
採用戦略を立てるときは、カスタマージャーニーを考えることも重要です。採用時点での求職者は、以下の行動を取ります。
| 認知→興味→応募→選考→オファー→内定通知 |
カスタマージャーニーを意識して、それぞれに適切なタイミングやチャネルで情報提供しましょう。
会社説明会や合同企業説明会など、オフラインでの手応えは可視化できない部分が多いため、主観的な分析となってしまうおそれがあります。カスタマージャーニーに適した情報提供ができているか分析するときは、明確なデータ(閲覧ページ数など)が取れるオンライン上の求職者の動きも参考にしましょう。
採用戦略の具体的な立て方
次に、採用戦略の具体的な立て方を順に見ていきましょう。
1.自社の採用体制を把握する
まず、自社の採用体制を整理します。具体的に、以下の点を把握して採用体制を再確認しましょう。
■募集枠の決定
新卒なのか、中途なのか、正社員なのか、パートやバイトなのかの決定です。複数の枠を募集する場合は、それぞれどれくらい募集するのか整理します。
また、募集対象ごとに何を重視するのかも明確化しておきましょう。一般的に期待される特性は以下のとおりです。
・新卒:熱意や成長性、柔軟性
・中途:即戦力やスキル
・正社員:企業文化や理念に沿った働き方ができる
・パート、バイト:長期間の勤続が可能
正社員は、第一に会社の理念を理解したうえで適切に行動できることが求められます。責任をもって仕事に従事することはもちろん、事業内容によっては異動や転勤が可能なことも条件にあげられるでしょう。
パートやバイトとして雇う場合、正社員のような長時間労働を求めることは容易ではありません。採用コストの削減や業務効率を重視すると、長期間の勤続が可能なことや、会社の利益のために行動できることが重要です。
■採用コストの見積り
予算内で採用活動を進められるよう、人件費などの内部コスト、広告掲載料や人材紹介会社への紹介料など外部コストの概算を出しておきます。
2.採用ターゲットを明確にする
採用ターゲットを理解するためにも、カスタマージャーニーを図式化し、後述するペルソナ設定などフレームワークと組み合わせてターゲットを明確化する必要があります。
採用ターゲットの明確化は、ユーザーのボリュームゾーンが異なる募集媒体を選定する際にも役立つため、しっかり設定しておきましょう。
3.採用活動の動きや受け入れ体制を整備する
次に、採用活動がスムーズにいくよう、受け入れ体制などを整備していきます。
■募集媒体の選定
設定した採用ターゲットなどをもとに、自社の求める人材に対応した募集媒体を選択することが重要です。
新卒で営業職を募集する場合は、求人サイトや採用イベント、SNSを活用しましょう。中途採用でスキルを重視する場合は、不特定多数にアプローチする求人サイトや採用イベントは非効率といえます。人材紹介やスカウトメール、SNSでピンポイントに募集をかける方法が効果的です。
管理職を採用したい場合も、人材紹介がおすすめです。リファラル採用で従業員の人脈を活用する方法もあげられます。
地方で採用するなら、地方自治体や企業が主催する、地方に特化した採用イベントがおすすめです。求人サイトやSNSも活用しましょう。
■面接官の決定と育成
面接官は、応募者にとって企業イメージにもなります。応募者からのイメージも意識して、短時間で人材を選考できるような面接官を育成することが重要です。面接官を複数設定する場合は、面接官の間で認識にずれが生じないように相互間の確認もしておく必要があります。
■マニュアル化
採用活動のたびに採用の基準が変わったり、求職者への対応が変わったりすると、求職者に不信感を与えてしまいます。担当者が変わっても同じように対応できるよう、マニュアル化なども進めておくと良いでしょう。
4.全社的な協力体制を取る
優秀な人材の獲得は、採用担当だけでできるものではありません。より良い人材を獲得するためにも、経営層や他部署に協力を仰ぎ、会社全体を巻き込んで採用活動を進めていくのが理想です。
たとえば、募集する部署内でのヒアリング、自社採用ホームページでの情報の開示などは、会社全体を巻き込むことでできるようになります。幅広い意見を聞くことによって、社内での認識のズレや人材のミスマッチも軽減できるでしょう。
このように、PDCAを回していくことで、採用業務の指針は固まっていきます。これらの採用戦略をスムーズに進めるなら、採用活動を一括管理できるTalentClip (タレントクリップ)の活用が効果的です。
TalentClipなら、以下のようなことが可能になります。
・求職者データを蓄積できる
・システム上で進捗を一元管理できるので無駄なくアプローチできる
・自社採用ホームページが簡単に作れる
・一括管理による負担軽減で採用活動の均一化が図れる
採用戦略を成功させるためにも、TalentClipの活用を検討ください。
採用戦略に活用できるフレームワーク
採用戦略で活用できるフレームワークをいくつか紹介します。
ペルソナ設定
ペルソナ設定は、採用ターゲットをもとに、架空の人物像を作り上げるマーケティング手法です。採用計画に関連づけ、年齢や趣味、性格、スキル、など具体的に設定します。
ほしい人材の特徴を羅列するのではなく、どのような人物なのか、ターゲットの分析を生活レベルまで落とし込めるのが特徴です。採用ターゲットについて、具体的なイメージがつかみやすいため、必要なアプローチも明確にできます。
1.人員計画のためのヒアリングをする
まずは自社の経営戦略に合わせて、どのような人材が必要なのかを経営者層と認識を合わせておきましょう。具体的にどのようなスキルをもつ人がほしいのか、人数を検討し、さらに各事業部で必要とされるスキルや価値観、性格なども考慮します。
会社全体で共通するところから各事業部の特徴へと、徐々にブレイクダウンしながら進めるとスムーズに整理することができるでしょう。
2.人物像作成に必要な情報収集をする
前の段階で明確になった要素や人数から、より具体的なペルソナ像を作成するために、社内でヒアリングを行いましょう。いくつかのペルソナ像が想定される状態から、「こういう人を求めている」といえる状態まで絞り込んでいきます。
ここでヒアリングする情報は多ければ多いほど良い、細かければ細かいほど良いというわけではありません。採用戦略を立てる上で必要な情報、たとえばどんな媒体に目を通しているのか、どこで接点がもてるのか、やりがいを感じることや価値観などを重視してヒアリングするようにしましょう。
3.仮のペルソナを設定する
ヒアリングが終了したら、ペルソナ像を設定してみましょう。経営者層や現場の担当者とも共有し、自社の経営戦略や現場の感覚とずれていないかを確認して、必要な修正をしたらペルソナ像の完成です。
経営者層も現場も理想を追い求めすぎるあまり、レベルの高い非現実的なペルソナ像ができ上がることがあります。その点は人事部が冷静に判断して、採用可能な人物かどうかを見極めるようにしましょう。
4.設定したペルソナを活用する
ペルソナ像が完成したら、採用戦略や実際の選考で活用していきましょう。応募者を集める方法や、選考の回数、方法などはペルソナに合わせた形で計画することが重要です。
面接の際にもペルソナ像は活用できます。特に人事部以外の社員が面接にあたる場合、合否の判断が面接担当者によってブレが生じやすくなります。事前にペルソナ像や重視するポイントを共有しておけば、そのようなブレも少なくすることができます。
事前の周知はもちろん、当日も活用できる準備シートなどを用意しておくと効果的でしょう。
3C分析
3C分析は、以下の3つのCを活用したフレームワークです。
1.Customer(市場・顧客)
2.Competitor(競合)
3.Company(自社)
採用戦略では、顧客を求職者、競合を採用市場での競合他社に置き換えて分析します。3つのCの特徴やニーズの分析を行うことによって、自社の強みを整理することが可能です。自社独自のアピールポイントを見つけるのにも役立ちます。
1 Customer(市場・顧客)
1つ目の「Customer」では、以下の項目に沿って分析します。
・候補者は転職先を選ぶときにどのような点を重視しているのか
・現在の採用市場で候補者となる人の数はどのくらいいるのか
・候補者となる人はどのようなタイミングや条件で転職を検討するのか
2 Competitor(競合)
2つ目の「Competitor」では、以下の項目に沿って分析します。
・採用においてどのような企業が競合となるのか
・競合他社はどのように採用活動を行っているのか
・競合他社ではポジションや条件などどのような待遇で採用活動をしているのか
3 Company(自社)
3つ目の「Company」では、以下の項目に沿って分析します。
・自社の採用における強みや弱みはどこにあるのか
・自社にブランド力やネームバリューはどのくらいあるか
・独自のサービスや商品は何か
・仕事のやりがいや面白みはどこにあるか
・給与や賞与、福利厚生などの待遇はどうか
4C分析
4C分析は、以下の4つのCを活用したフレームワークです。
1.Customer Value(顧客価値)
2.Cost(顧客負担)
3.Convenience(顧客利便性)
4.Communication(コミュニケーション)
採用戦略では、求職者の立場で、顧客価値を入社するメリット、顧客負担を入社するデメリット、顧客利便性を日程調整などのしやすさ、に置き換えて求職者目線で自社を分析します。
内定や入社までのフローで問題がないか、問題があればどのようにして解決できるかを考えるために役立つフレームワークです。
1 Customer Value(顧客価値)
まずは、求職者が企業に求める価値から、自社が求職者に対して提供できる価値を定義します。仕事内容だけでなく、待遇や職場環境、企業のネームバリューなど広くとらえることが大切です。このような価値を一つの束と捉えて採用戦略を組み立てていきましょう。
2 Cost(顧客コスト)
企業が提供する価値に対して、求職者がそれを手に入れるためにどれくらいのコストをかけられるのかを検討します。採用の場面においては、具体的には転職のリスクなどが挙げられるでしょう。採用市場の情報や競合他社の情報を踏まえつつ、求職者にとって価値とコストが見合っているか、改善できるところがないかを検討する必要があります。
3 Convenience(利便性)
求職者がその価値を手に入れる上で、どのくらいの手間や時間がかかるかも検討しなくてはなりません。採用にかかる時間ややり取りがスムーズにできるかなど、求職者に不便を感じさせないような工夫が必要です。
競合他社よりもはるかに速いレベルは必要ありませんので、他社と比べて劣らないレベルを維持するようにしましょう。
4 Communication(コミュニケーション)
採用活動を進めるためには、求職者に自社の存在を知ってもらわなくてはなりません。さまざまな広告やメディアでの情報提供が必要になりますが、求職者がそれらに利益を見出さなければ有効にならないので注意が必要です。
求職者がどのようなコミュニケーションを求めているのかを考えた上で、広報戦略を練っていきましょう。近年はオリジナルの採用ページを用意する企業も増えていますが、それらはコミュニケーションの視点から生まれたものといえます。
SWOT分析
SWOT分析は、以下を分析するフレームワークです。
1.Strength(強み)
2.Weakness(弱み)
3.Opportunity(機会)
4.Threat(脅威)
環境要因をもちいて分析する方法で、3C分析や4C分析と組み合わせることによって、より良い効果が期待できます。自社を理解するのに適した手法です。
上述したフレームワークを活用すれば、採用活動をより効率良く進めることができるでしょう。
以下の資料では、採用活動に役立つ情報を紹介しているので、採用活動でお困りの方はぜひご参考ください。
1 内部環境の分析
内部環境とは、自社の「S:強み」や「W:弱み」にあたるものです。自社がもつブランド力や資産、提供している製品・サービスの価格や品質、働く社員、組織、技術、設備などのことを指します。主観的ではなく、競合他社とも比較しながら客観的に分析し、自社の情報を整理することが重要です。
2 外部環境の分析
外部環境は、自社の「O:機会」と競合他社の「T:脅威」にあたるものです。自社の努力では変えることができない、競合他社の特徴や顧客のニーズ、市場のトレンド、景気、法律や政治・経済の動向、国際情勢などが当てはまります。外部環境を分析することで、自社にはどのような機会があるのか、脅威となっているのはどのようなものなのかを把握します。
採用戦略を成功に導くためのポイント
採用戦略を立てるからには、コストに見合った成果を得たいものです。そこで、採用戦略を成功に導くためのふたつのポイントを紹介します。
内定者へのフォロー体制を整える
採用活動は、内定通知を行えば終わりではありません。採用したい人材に確実に入社してもらうためには、内定後のフォローをしっかり行えたかどうかが重要です。
内定後に何のフォローもなければ、せっかく採用しても会社から内定者の気持ちが離れてしまいます。他社からも内定をもらっていれば、こまめなフォローを行った会社に優秀な人材が流れてしまうでしょう。
入社までしっかりと内定者の気持ちを掴んでおくために、内定後のフォロー体制を整えておく必要があります。担当者を決めるだけではなく、内定者が上司や先輩へ相談しやすい雰囲気作りも重要です。
PDCAサイクルを回し続ける
時代によって売り手市場・買い手市場が変化するように、求職者の傾向も変化します。一度作成した採用戦略が、何年も通用するとは限りません。
より効果的に採用活動が行えるよう、PDCAサイクルを回し続けることが重要です。
・Plan(計画):採用戦略を立てる
・Do(実行):戦略に沿った採用活動を行う
・Check(評価):採用実績を評価する
・Action(改善):課題を見つけ、対処する
上記のサイクルを年度ごとに繰り返し、採用戦略の改善すべきポイントを洗い出し対処して次年度に活かしましょう。
まとめ
採用活動を円滑に進めていくためには、フレームワークを活用した採用戦略をしっかり立てることが重要です。採用戦略をスムーズに実行していくには採用管理も重要になりますので、採用管理システムの導入など管理体制も見直していきましょう。
また、効率良く採用活動を進めるには、採用のタイミングも意識する必要があります。採用のタイミングについて、さらに詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。