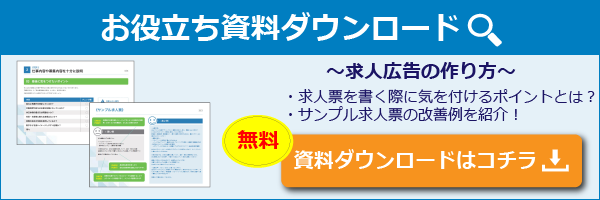採用の歩留まりを改善する方法7選|歩留まりの平均や分析、計算方法
採用活動を進めるなかで、人事担当者を悩ませるもののひとつに、「歩留まり率」が挙げられるでしょう。
採用フローのなかで、選考や面接などを途中で辞退する応募者数の指標となるものですが、改善するのはとても困難です。
今回は、少しでも良い人材の確保につながるよう、採用における歩留まり率の改善方法を紹介します。
そもそも採用の歩留まりとは?
採用の歩留まりとは、採用の選考過程において各段階に進んだ人数の割合のことを指します。その割合を%で表した数字が、歩留まり率です。
まずは、歩留まりの計算方法や分析の仕方を紹介します。
採用の歩留まりを計算する方法
採用の歩留まりは、以下の式で算出できます。
歩留まり率(%)=選考過程を通過した人数÷選考過程の対象となる人数×100
たとえば、内定者数10人に対して実際に入社した人数が6人であれば、採用の歩留まり率は60%です。歩留まり率が高いほど、次の選考フェーズへの通過者が多く、歩留まり率が低いほど脱落者が多いと捉えられます。
自社の歩留まりを分析する方法・項目
一般的に、学生の採用フローはエントリー、説明会予約、説明会参加、書類選考、筆記試験、面接試験、内定、内定承諾、入社と続きます。それぞれの採用フローで、歩留まり率が算出でききるため、学生が踏む手順を詳細に書き出し、何人が選考を通過したかを正確に把握することが大切です。
<採用フローと歩留まりの算出例>
| 各選考過程での歩留まり率 | 算出方法 |
|---|---|
| 受験率 | 受験者数÷エントリー数×100 |
| 説明会予約率 | 1説明会予約者数÷エントリー数×100 |
| 説明会参加率 | 説明会参加者数÷説明会予約者数×100 |
| 面接予約率 | 面接予約者数÷書類選考通過数×100 |
| 面接参加率 | 面接参加者数÷面接予約者数×100 |
| 面接通過率 | 面接通過者数÷受験者数×100 |
| 途中辞退率 | 途中辞退者数÷受験者数×100 |
| 内定辞退率 | 内定辞退者数÷内定者数×100 |
| 内定率 | 受験者数÷内定者数×100 |
極端歩留まり率の低下は、その選考過程で学生が離脱するなんらかの理由が生じたと判断できます。このように、歩留まりを分析することで採用における課題が明らかになるため、具体的な改善策を立てるのに役立つのです。
新卒採用における歩留まりの平均
ある調査にて新卒採用における歩留まりの平均は、以下のようになっています。歩留まりは「採用予定数を100」とした場合の内定出し人数、内定辞退人数、内定人数の数値から算出しています。
| 従業員規模 | 歩留まり率 |
|---|---|
| 300人未満 | 54.9% |
| 300~999人 | 52.8% |
| 1,000~4,999人 | 52.5% |
| 5,000人以上 | 43.6% |
歩留まり率は大企業より中小企業の方が高めです。全体では50%前後を推移していて、内定者の約半数しか承諾に至らないとわかります。
採用の歩留まり率が低くなる5つのタイミング
歩留まり率を改善するためには、まずは割合が低くなるタイミングについて把握しておく必要があります。
代表的なタイミングが5つありますので紹介しましょう。
1.「応募」~「会社説明会」
この時期は、採用フローの始めでもあり、歩留まり率が大きく下がりやすいタイミングです。
応募直後はモチベーションも上がっている状態ですが、時間が経過すると少しずつ気持ちが冷めてしまいます。
せっかく興味を持ってくれた応募者を逃さないためには、応募後なるべく期間を空けずに会社説明会を実施することが大切です。
会社説明会は、自社の魅力をアピールできるチャンスでもありますが、参加してもらえなくては意味がありません。
早めの行動を取ることで、応募者のモチベーションが高いうちに説明が実施でき、より会社への興味を高めることができるでしょう。
2.「書類選考・試験」~「一次面接前」
この期間は、企業側にとっては人材の絞り込みを行う段階であり、応募者も説明を受けた結果で選考に進むか考える段階なので、双方が判断をするタイミングです。
もともと人材が絞り込まれる時期のため、歩留まり率の低さは必ずしも問題というわけではありません。
とはいえ採用予定人数に対して応募者が少な過ぎるようであれば、応募者の時間や負担を減らす工夫が必要でしょう。
例えば、この段階までのフローを簡素化して、説明会と選考試験や面接と試験を同日に実施するなど、スケジュールを1日にまとめることで日程を調整する負担は軽減できます。
そもそも予定人数より少な過ぎるというのは、採用活動自体にも問題があるかもしれません。
今後の人材確保のことも考えると、採用手法やアプローチ方法を見直す必要もあるでしょう。
3.「面接設定」~「面接」
この面接設定から面接の時期は、採用フローにおいて最も歩留まりが低下しやすいタイミングです。
面接の際には求人者が会社を訪れることがほとんどですが、一次面接・二次面接問わず、会社に訪問して面接を行うということ自体が精神的ストレスを感じてしまうということもあるようです。
また、面接の内容によって内定に大きく影響を与えるということもプレッシャーに感じてしまいます。
面接は採用フローとしても重要ですが、応募者側の精神的ストレスもあり歩留まりの低下につながりやすくなります。
面接の段階では、競合他社との内定出しの時期と重なることもあり、そういった場合も辞退者が増えるでしょう。
そのため、競合の採用状況も把握しながらスケジュールを組むことも大切です。
4.「内定出し」~「内定承諾」
この段階では、応募者の希望に合わない、企業に魅力を感じないなどが辞退の原因であることが多く、歩留まり率の低下で一番問題視される部分です。
面接で具体的な仕事内容や待遇を聞いて合わないと判断される場合は、そもそも事前の情報提供が不足していると考えられます。
募集要項を掲載している内容や説明会の質をもう一度見直した方が良いでしょう。
さらに、魅力を感じてもらえず、結果的に辞退してしまうというのは大きな問題で、どのような点が競合に劣っていたのか、どこのアプローチが不足しているのか、採用フロー全体を通して考えなければいけません。
面接官の言動が辞退の要因となることも多いので、人選や教育を徹底して企業の信用を損ねないようにしましょう。
5.「内定承諾」~「入社」
入社直前になって、企業に対して不満や不信感などが出てしまうケースも多く、承諾前の段階と同様に問題です。
労働条件のミスマッチ、または不明瞭なのに内定承諾を促されたなどが原因となる場合もあります。
労働条件を正しく提示・説明すること、不信感を与えた原因の追求をして早急に改善しましょう。
以下の資料では、採用活動をスムーズに行うためのお役立ち情報を紹介しています。採用活動全般における課題を少しでも早く解決したい方は、ぜひご覧ください。
採用の歩留まり率の低さを改善する方法7選
ここからは、どのようにして歩留まり率を改善するか紹介します。
1.応募者への対応は早く行う
応募者への対応は、すべてにおいて早く行うことが重要です。
応募後の対応は、就業意欲が高い当日中に行うことを基本にしましょう。応募がきたらすぐに返信して連絡を行うようにしてください。
優秀な人材であれば複数の内定を取得しているので、内定出しや労働条件の提示なども他社より早く行うことが大切です。
応募者との連絡調整の方法としては、メールや電話だけでなく、LINEなどのアプリの活用も検討してみるのも良いでしょう。
普段から使う頻度も多くなっているコミュニケーション手段なので、日程の調整などの際はレスポンスも早くなり、相手が既読になっているかも確認が可能です。
また、社内で採用活動に関する情報共有ができていると、対応のレスポンスを早める効果も期待できます。
特に、会社が求めている人材の具体的な希望があれば、その情報をしっかりと共有しましょう。
そうすることで、採用に関わっている社員の意識が統一され、応募者に対する選考なども容易になります。
多くの応募者の中から内定者を決める作業は、多くの判断が必要となり、意識の統一は作業スピードを上げるためにも重要です。
結果的には、応募者を待たせる時間も短縮できるでしょう。
2.採用フローの短縮を図る
多くの業務を抱えた状態では、素早い対応を行い続けるのは困難でしょう。
安定して応募者への対応を早くするためにも、採用フローに要する期間の短縮を図ることも大切です。
期間の目安としては、新卒採用は1ヶ月以内、中途採用は2~3週間以内でそれ以上に時間がかかっている場合は見直しが必要となります。
3.入社意欲を高める動機付けを行う
入社辞退を防ぐには、採用候補者の入社意欲が高まるような動機付けを行うことが重要なポイントです。とくに面談や座談会など、採用候補者と直接コミュニケーションを取る場は、動機付けを行う機会として最適です。
採用候補者は、社員と話す機会を通じて、会社で働く様子や将来のキャリアなどをイメージしやすくなります。
歩留まり率を改善するには、選考過程のどの段階でどのような動機形成をするか決めて、計画的に進めていく必要があります。そのために、入社の決め手や入社後のモチベーションなどについて、現在いる社員にヒアリングをしておきましょう。
4.積極的なクロージングを行う
内定者に対し、会社側がフォローするとともに入社の意思を固めてもらう「クロージング」も重要です。「ぜひ採用したい」と思う内定者は他社からの引き合いも多いと考えられるため、内定辞退を防ぐためにも積極的にクロージングを行いましょう。
よく行われるクロージングの方法として、昼食会や社内見学会があります。クロージングは、面接などの選考時よりもフランクに話をしたり、社風を伝えたりする場にします。
特に、新卒の内定者は社会人経験がないので、新しい生活や仕事に対する不安があるかもしれません。採用担当者はそのような悩みごとに寄り添い、フォローすることが重要です。社会人の先輩として、不安を和らげたりアドバイスをしたりして「この会社でならがんばれそう」と内定者に感じてもらえるようにしましょう。
なお、新型コロナ対策を重視するなら、オンラインでの説明会やランチ会という形をとるのも良いでしょう。
5.面接官への指導を行う
面接官は応募者にとって会社の印象を決定づける存在です。応募者が「この会社に入社したい」と思うかどうかは、面接官次第といっても過言ではありません。応募者に好印象をもってもらうためには、面接官の教育が大切です。
今は、「企業が応募者を選ぶ」のではなく「応募者が企業を選ぶ」環境にあります。面接官には「応募者から選んでもらうために必要なことは何か」といった観点で、応募者と向き合うよう指導します。「上から目線」で臨むと、会社の評価を落とす可能性もあるので注意が必要です。具体的には、以下のような事柄について指導、教育を行います。
・面接官の心構え
面接官は応募者に安心感を与える存在であることを伝える。
・応募者とのコミュニケーションの取り方
質問すべき内容としてはいけない内容、欲しい情報の引き出し方を指導する。
・面接の流れや評価基準
どのような流れで面接を進めるのか、どこに着目して評価すべきかを明確にする。
また、実際の面接の前に社内でロールプレイングを行い、求められる面接官の役割を担当者ができているかチェックと指導をしておきましょう。
6. 学生からのフィードバックを受ける
説明会や面接が終了したら、学生にアンケートやヒアリング調査を実施しましょう。学生からの客観的な意見を聞けば、採用活動の課題が明確になります。
とはいえ、率直な意見を聞くためには、調査の際に「選考には一切関係がない」「今後の採用活動に活かすための取り組みである」の2点をしっかり説明する必要があります。
7. 採用活動の一部を外注する
人手不足で学生に対して丁寧な対応ができない場合は、採用活動の一部を外注するのも良い方法です。リソースに余裕ができ、歩留まり率の改善も見込めます。
採用活動の負担軽減には、自社に合うツールや採用管理システムを導入するのもおすすめです。
まとめ
今回は採用における歩留まり率の改善方法について解説しました。
採用フローの中では、多くのタイミングで辞退につながるリスクがあります。できる限り防止するためには、応募者へ素早くも丁寧な対応が必要でしょう。
採用業務の見直しを行っても対応が遅くなる場合は、業務の効率化が行える採用管理システムのTalentClipをご検討ください。
歩留まり率を改善するには、応募者への電話・メール対応も丁寧に行わなければなりません。
電話・メールでの対応方法について詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。例文付きでご紹介しています。