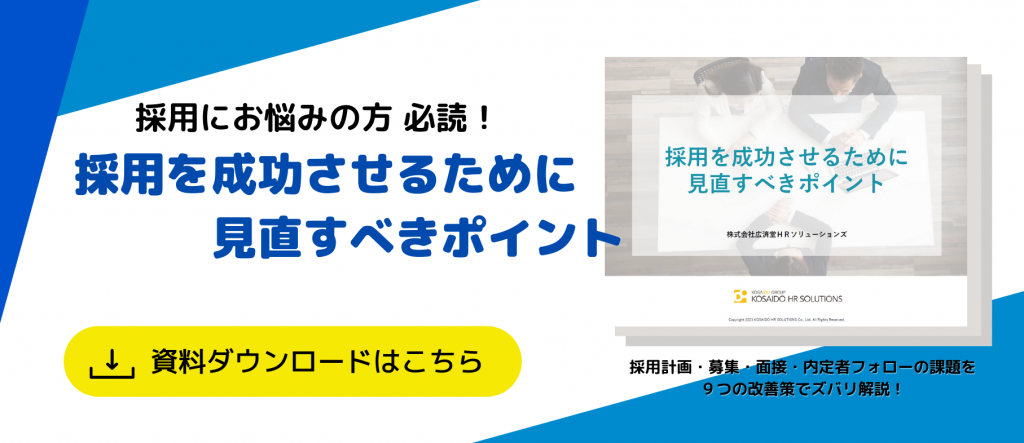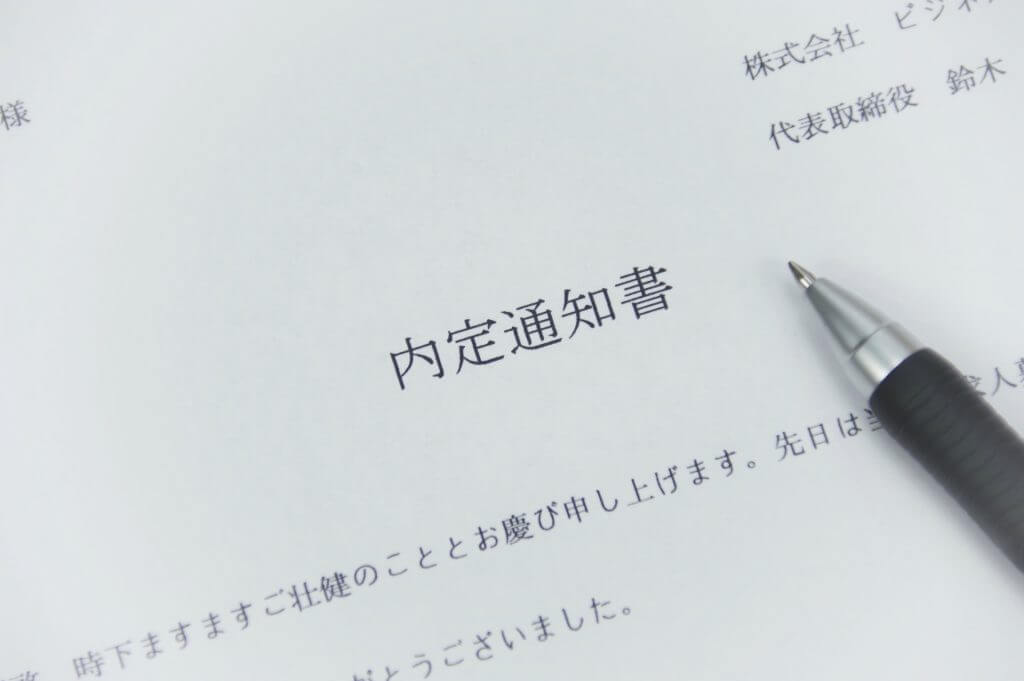
内定承諾率を上げるために採用担当者ができる施策
内定までいっても辞退が多く、採用者が減少していると悩みを抱えてはいないでしょうか。内定辞退が多いのには理由があります。この記事では、内定承諾率が低い企業の特徴と内定承諾率改善の方法について見ていきましょう。
【当てはまっていない?】内定承諾率が低い企業の特徴
内定承諾率が低い企業には、共通する特徴があります。主なものは、以下の3つのような特徴です。
自社の魅力を伝えきれていない
売り手市場であっても、就職先がすぐに決まるとは限りません。特に新卒の場合であると、しっかり準備して、複数社にエントリーしているケースも多いです。エントリーした企業から複数内定があると、応募者は内定のあった会社から就職先を選択できます。
どの企業を選択するかは応募者の第一志望なども影響してきますが、最終的には一番魅力を感じた企業を選択することになるでしょう。
つまり、逆にとらえれば、魅力を感じない企業は真っ先に内定辞退の対象となるということです。応募者のなかで第2、第3と優先順位が落ち、「ほかの企業から内定をもらった」という理由で内定辞退をされるのです。
優先順位が応募者の中で落ちるのは、自社の魅力が応募者によく伝わっていないことが原因ではないでしょうか。発信力の低い企業、選考段階でアピールが十分にできていない企業は、内定承諾率が低い傾向にあります。
対応スピードが遅い
内定承諾率の低さは企業の対応スピードも関係しています。たとえば、2社応募していたとして、一方の返答が遅かった場合、応募者はどのように感じるでしょうか。
なかなか電話がつながらなかったり、メールの返信がこなかったり、何の連絡もないまま選考が長引くと、不安に感じる応募者も出てきます。たとえ企業側に故意がなくても、企業から必要な人材と思われていないのではと考える応募者もいるでしょう。
このように、企業側の対応スピードが遅く、応募者が不安や企業への不信感、不満を感じて内定辞退になるケースがあります。
一向に選考が進まず状況が見えない企業に就職するよりも、自分が必要とされていると感じる、対応が早く誠実な企業に勤めたいと思うからです。
あわせて読みたい ☞
応募者に対しての態度が悪い
応募者に対する態度が良くない企業も内定承諾率が低いです。面接時に横柄な態度、威圧的な態度を取っていないでしょうか。良くも悪くも、選考段階で応募者が接することになる面接官や社員の印象は、その企業のイメージを背負います。
選考に携わる面接官、あるいは社員の行動が不信感や不安を与えていないか、教育体制は十分なのか注意が必要です。
【内定承諾率を上げる方法その1】基本的な施策
内定承諾率が低い理由を知ったら、原因を克服できるように動いていきましょう。先ほど伝えた原因に対して、内定承諾率を上げるための方法を紹介します。
1.採用ブランディングを行う
自社の魅力を伝えきれていないことが内定承諾率低下につながっているなら、採用ブランディングを行いましょう。
採用ブランディングとは、入社したいと思ってもらえるように、自社を採用においてブランド化することをいいます。端的に、自社の知名度を上げ、自社の魅力を知ってもらうことです。
具体的には、採用サイトの開設、就職説明会などのイベントへの参加、SNSを活用した情報発信などをとおして採用ブランディングを行います。求める人材を獲得できるよう、自社の価値をターゲットである応募者に知ってもらうことが目的です。
ターゲットを絞り、どのようなイメージをもってもらいたいか、効率の良い発信方法を考え、ブランディングしていきます。
2.応募者への連絡は早めにする
対応スピードが遅いと、内定承諾率が低くなりやすいと解説しました。内定承諾率を上げるには、応募者への連絡をスピーディーに行うことが重要です。
応募者から連絡があれば、可能な限りその日のうちに返信するようにしましょう。休みをはさむ場合、あるいは確認が必要ですぐに回答できない場合は、その旨を伝えたうえで、いつまでに回答するかの目安を伝えておくと応募者も安心できます。
面接日程も早めに決めるのがポイントです。面接担当者がそろわないため面接を先送りにするのではなく、条件を緩和してできるだけ早く面接まで進めるようにしましょう。
面接結果も、特別な事情がない場合はできるだけスピーディーに伝えるようにします。応募者を不安にさせたり、不満を抱かせたりしないことが重要です。
3.社内でマナーについて考え直す
面接などで応募者が不快な思いをしないように、社内でマナーについて考えるのも内定承諾率を上げるポイントです。言葉遣いは適切か、態度に問題はないか、今一度対応を確認しましょう。
面接のなかにもあえて圧迫面接をするという手法はありますが、度を過ぎるとパワハラとして取られたり、企業のイメージダウンになったりします。対応が適切か、応募者を遠ざける要因になっていないか、場合によっては採用担当者自体を入れ替えることも考えるべきです。
【内定承諾率を上げる方法その2】プロセス管理をする
内定承諾率を上げるには、これまで紹介した方法に加えて、選考までの過程となるプロセス管理が求められます。プロセス管理をすることで、データを基にして対策を立てられるようになります。
まずはポイントとなる採用プロセスを把握する
内定承諾率を上げるためのポイントとなる採用プロセスは、次のとおりです。
「応募」から「会社説明会」
応募してから会社説明会まで日にちが空いてしまうと、せっかく会社に興味を持ってくれた応募者が興味をなくしてしまう恐れがあります。できるだけ早い段階で、説明会を開催できるようスケジュールを組みましょう。
「書類選考・試験」から「一次面接前」
書類選考から一次面接にかけての段階では、辞退者が増えることが多くなります。これは、説明会の内容を聞いて、「希望の条件とは異なる」と判断する人が出てくるためです。
多少の辞退者がいるのは想定内ととらえて問題ないのですが、あまりにも辞退者が多い場合は選考内容の再考が必要です。説明会当日に書類選考を兼ねた試験を行ったり、アプローチ先を変えたりするなどの工夫をしましょう。
「面接設定」から「面接」
この段階では、実際に企業へ来社するという応募者にとって心理面での大きなハードルがあるため、辞退率が高くなる傾向にあります。さらに、他社の内定が出る時期と重なると、辞退者はさらに増える可能性があります。
場合によっては、選考スケジュールを早める取り組みが必要です。
「内定出し」から「内定承諾」
この段階で内定承諾率が下がるのは、実際に働くイメージを想像できなかったり、面接で詳しく聞いた勤務条件が希望と合わなかったりすることが主な理由です。
また、面接官や担当社員の対応が不適切だと、会社への印象が下がってしまい、辞退者が発生しやすくなります。採用現場に立ち合う社員は、全員が「企業の顔」となることを再認識しましょう。
「内定承諾」から「入社」
内定時に提示された労働条件が希望と異なるケースや、担当者から内定承諾を早急に促されるケースなど、応募者の不信感が高まってしまうと、入社直前での辞退につながる恐れがあります。
プロセスごとの施策
プロセスごとで、ぜひ心がけたい施策には、どのような取り組みがあるのでしょうか。
選考中
選考段階において、応募者はさまざまな不安や疑問点などを抱えています。企業側からは、応募者の疑問点は分かりづらいことも多いため、どのような点が不安なのか、解決しておきたい疑問点はなにかを積極的にヒアリングしてみましょう。
また、応募者が知りたい情報と、企業側から伝えたい情報は、必ず一致するとは限りません。目の前にいる応募者が知りたい情報を、丁寧かつ正確に伝えるようにしましょう。不安が解消されることで、承諾率を上げる結果につながります。
内定後
内定後には、適切なフォローをすることで内定者の不安を解消し、承諾率を上げることができるでしょう。
面談や懇親会などの機会を設ける、実際に働く職場の見学やインターンシップを行うなど、入社後に働くイメージがわきやすくなるような取り組みが必要です。
これまで紹介したプロセス管理をスムーズに行い、内定承諾率を上げるには、TalentClip(タレントクリップ)の活用がおすすめです。TalentClipは、採用管理システムとして多彩な機能を搭載しています。採用HPの作成機能にテンプレートがついているため、初めて担当する方でも短時間でHPが作成可能です。
さらに、求人メディアであるWorkinやIndeed、求人ボックス、スタンバイ、Googleしごと検索などの求人サイトと連携しでき、応募者管理も一括で行えます。採用HPと求人票をまとめて作ると、企業をより理解した求職者を集めることができるため、内定率の向上にも効果的です。
さらに詳しい機能をお知りになりたい方は、お気軽にTalentClipまでお問い合わせください。
まとめ
内定承諾率が低い企業には、共通する理由があります。まずは、内定承諾率が低くなる原因を把握しましょう。把握した上で、どのような対策が必要か考えます。
採用ブランディングをする、応募者への連絡を早くする、採用担当者を教育するなど、状況によってできる対策はありますので、自社の様子を見て見直しを図りましょう。
また、採用環境を整えるには、計画を立て実行できるようにすることも重要です。日々の採用活動に追われて注力できないなら、採用管理システムをうまく活用して効率化を図ると良いでしょう。
内定承諾率を上げるには、内定者へのフォローを充実させることも重要です。こちらの記事では、内定者フォローのポイントをご紹介しています。