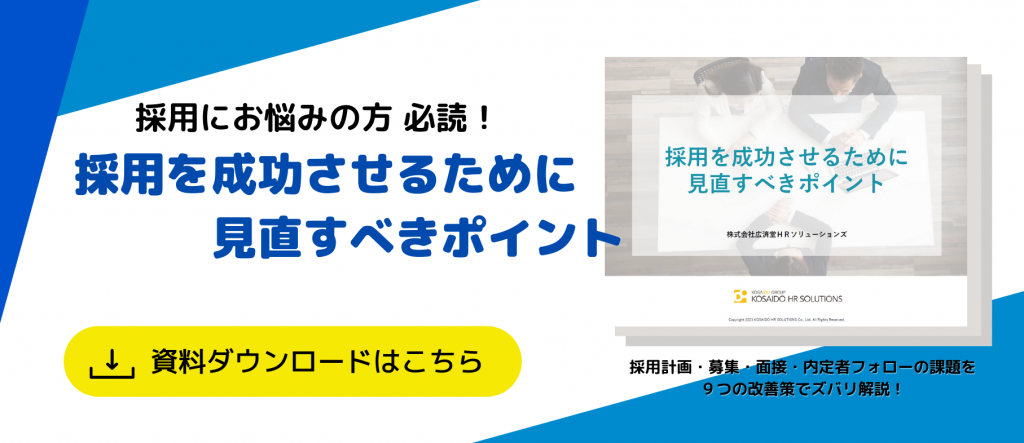採用率とは?採用率アップに必要な5つの工夫を採用フロー別に紹介
採用業務に追われていても、なかなか自社に合った人材を獲得できず、悩んでいる採用担当者は少なくありません。今回は採用率に焦点をあて、採用が伸び悩んでいるときの解決策を考えていきましょう。
あわせて採用率アップのためにできる工夫を採用フロー別に解説します。採用率を少しでも上げたいと考えている方はぜひ参考にしてみてください。
この記事の目次
採用率とは「応募者のうち採用した割合」のこと
まず、採用率は以下の計算式で導き出すことができます。
採用率(%)=採用者数÷応募者数×100
要するに採用率とは、応募者に対して何人を採用したのかパーセンテージで表したものです
たとえば500人の応募があり、5人を採用した場合の採用率は1%になります。
採用率の平均は業種や職種によって異なるため、一概にどれだけあれば高い、低いと判断することはできません。自社の採用活動の結果を把握する、ひとつの数値であると認識しておきましょう。
採用率の根本課題を探るなら「歩留まり」を把握しよう
採用率が低いと感じたら歩留まり(ぶどまり)を確認してみてください。歩留まりとは採用活動のフローを進み、次の工程へ進んだ人数の割合をさす言葉です。
さまざまな策を講じても採用率が改善しないと感じるなら、採用フローのどこかに問題があるのかもしれません。以下に採用フローの一例を挙げました。
・募集活動
求人サイトやSNSを用いて求人情報を掲載し、応募者を募ります。
・会社説明会
応募者に向けて会社の事業内容や社風など、自社についての情報を説明します。
・選考
書類選考や筆記試験を実施し、応募者の適性を判断します。
・面接
1対1ないしグループでの面接を実施するほか、応募者にグループディスカッションをさせ、それぞれの言動から適性を見極める場合もあります。一次、二次と複数回にわたり面接をする企業も多いです。
・内定
適性ありと判断された応募者に内定通知を行います。
・入社
正式な入社手続きを行います。内定から入社までの期間に研修や懇親会を実施する場合もあります。
採用活動に関する課題を見つけるには、まず自社の採用フローを書き出してみましょう。そして歩留まりを確認してみてください。
たとえば、会社説明会から選考の過程で歩留まりが低いなら、会社説明会の内容になんらかの課題があるのかもしれません。課題がわかれば改善もできるでしょう。
【採用フロー別】採用率をアップさせる5つの工夫
続いて、採用率アップのためにできる工夫について考えていきます。採用フロー別に試せることをまとめましたので、参考にしてみてください。
【募集活動】求人媒体を見直す
募集活動を行う際は、応募者のターゲット層がよく利用していると思われる媒体へ情報を掲載するようにしましょう。求人情報や求人広告を出すにしても、ターゲット層が見る媒体に掲載しなければ見てもらえません。
いまや20代のほとんどが当たり前にスマートフォンを持っています。企業や求人に関する情報収集は、ネット上で行われることを前提に考えておきましょう。とくに、求人応募の前には、企業のホームページに目を通していることが多いです。
また、SNSの利用率が高いのもこの層です。求人媒体とSNSを連携させれば、より多くの求職者からの応募が期待できます。
採用ページづくりや求人掲載に関して悩みがあるなら、オールインワン型採用管理システムのTalent Clip(タレントクリップ) のご活用を検討してみてはいかがでしょうか。
Talent Clipではプロが採用ページを制作します。制作作業はプロのカメラマンやライターが担当するため、採用ページ制作にかかる作業時間と手間を削減することが可能です。空いた時間を別の採用活動にあてることもできます。
また、Talent ClipはIndeedやGoogleなどの大手求人媒体との連携も可能です。集客に力を入れたいときにも役に立つことでしょう。
応募者の管理から面接対応、スケジュール管理、内定者が入社したあとのフォローまで一括で管理できます。採用業務のコスト削減をお望みなら、ぜひTalent Clipへお問い合わせください。
【会社説明会】知りたい情報・ここだけしか聞けない情報を伝える
会社説明会で、求職者が聞きたい、知りたいと思っている情報について話ができているでしょうか。すでにホームページやSNSに掲載している内容を話しても、求職者はつまらないと感じてしまいます。
求職者が知りたいのは、仕事内容と求める人材像、そして社内の雰囲気です。これらの項目について会社説明会でしか聞けない内容をあらかじめまとめておき、話しましょう。
求職者の記憶に残る会社説明会を実施し、良い印象を与えることができれば、選考へ進んでくれる可能性も高くなります。
一方で、冗長的な話や資料を読み上げるだけでは求職者を退屈にさせます。伝えたいことをわかりやすく簡潔にまとめ、ときには写真や動画も活用しながら、伝えたいことがきちんと伝わる会社説明会を実施してください。
【書類選考】選考基準を明確にする
どんな人材を採用したいかによって、求めるスキルやこれまでの経験、持っていてほしい資格などの条件はさまざまでしょう。
そのような人材要件が不明瞭な場合、採用担当者によって評価にずれが生じる可能性があります。適性のない人材も選考に通過してしまうなど、ミスマッチが起こる原因となります。
まずは、選考基準を明確にしましょう。採用担当者同士で人材要件について共通認識をもっておけば、自社に合う人材を効率的に採用できます。
既存の採用基準を最適化する方法については、以下の記事で詳しく説明しています。
【面接】ドタキャン対策を行う
面接でドタキャンや辞退される件数が多いと歩留まりは低くなってしまいます。ドタキャンや辞退が起こる理由のひとつに、「同時に進めていた他社の選考で内定が出て、面接に行く必要がなくなった」という状況が考えられます。
要するに、自社より早く選考が終わった他社に求職者が流れてしまったということです。このような事態を避けるため、書類選考から面接まではあまり日を空けないほうが良いでしょう。書類選考に通った求職者に対しては、すぐに選考通過と面接実施の連絡を入れるのがおすすめです。
また、面接実施日の候補は複数出し、日程は近くにします。書類選考から面接までの期間が1ヶ月も空くようでは、求職者はほかの企業の選考を進めてしまうでしょう。遅くとも1週間以内には実施できるよう、求職者に日程を提案してみてください。
面接実施日の前日にリマインドメールを送るのも大切です。多忙な求職者がうっかり面接をドタキャンしてしまわないよう、リマインドメールで面接日を思い出してもらいましょう。
【内定】内定者フォローを充実させる
求職者に内定を出したから安心とは言い切れないのが採用の現場です。内定辞退が多くなれば歩留まりは当然低くなります。
入社前の内定者の不安が少しでも軽くなるよう、内定者フォローは徹底すべきです。社員との面談や座談会を開催して内定者の疑問を解消するよう働きかけるのが良いでしょう。
内定者同士でのコミュニケーションの場をつくるのもおすすめです。内定者同士でやり取りできる専用サイトを用意したり、気軽に参加できる社内イベントを開催したりして、内定者が入社後にすんなりと会社に馴染める環境づくりをしてあげてください。
内定者フォローの施策については、以下の記事で詳しく紹介しています。
【内定者フォロー】内定辞退率を下げる方法とポイントを解説!
まとめ
採用率の基準は企業により異なります。自社が考える基準より低いと感じるときは採用フローの課題を見つけて改善しましょう。各採用フローの歩留まりを上げることができれば採用率も上げることができるはずです。
募集活動のやり方を見直す、会社説明会の内容を再考する、選考の基準を再確認するなど、工夫できることはたくさんあります。
社内の採用担当者同士で足並みをそろえ、より良い人材確保のためにできることを考えてみてください。