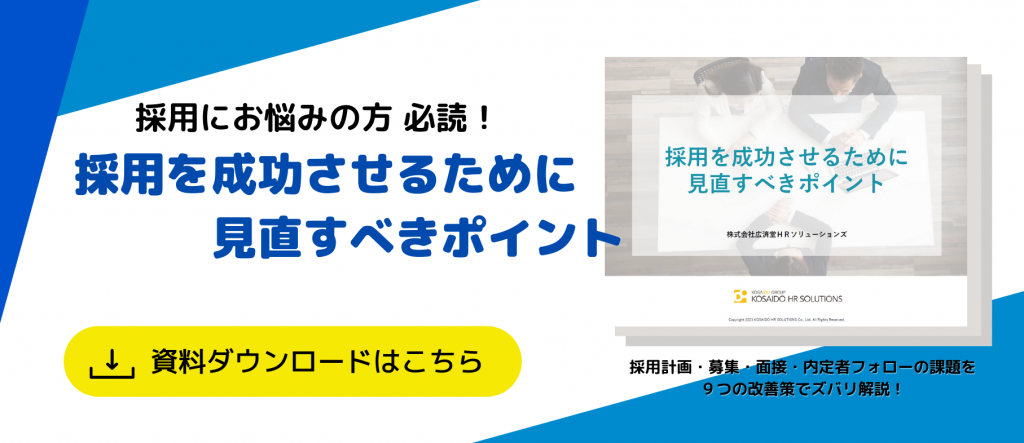採用サイトとは?求職者が応募したくなる採用サイトの作り方
採用サイトの運営は、企業にとって数々のメリットがあります。
自社で運営する採用サイトには制限がなく、決められた情報しか載せられない広告媒体よりも、詳細な情報が発信できます。求職者に対して、企業はより多くの情報を伝えることができるため、採用成功率も大きく上がります。
今回は、採用サイトの基礎知識や、制作のポイント、得られるメリットなどについて詳細を解説していきます。
採用サイトとは
採用サイトとは、その名のとおり人材の採用を目的としたサイトのことで、運営の狙いやコンテンツは、コーポレートサイトと大きく異なります。
そこで、まずは採用サイトの基本的な概要、コーポレートサイトとの違いからお伝えします。
採用サイトは「採用のためのホームページ」
採用サイトとは、自社の募集要項や選考フロー、求める人物像などが記載された、採用活動のためのサイトです。
ターゲットは求職者になるため、サイト内のコンテンツも自社の採用に関する情報がメインとなります。
また、現代では多くの人が情報収集の手段として、インターネットを利用しています。
ほとんどの求職者は、企業の情報を得るために、志望している会社のコーポレートサイトを真っ先に確認しています。それだけ、求職者の企業に対する関心度が高いことがわかります。
求職者の企業に対する関心の高さを利用し、コーポレートサイトに加えて、自社の採用サイトを運営に取りかかりましょう。採用サイトを運営することで、求職者により多くの採用情報が発信できます。
企業は、採用に関する情報を多く発信することで、求職者に向けてアプローチが行えます。結果、応募者の増加や、母集団の形成の成功へと直結するのです。
コーポレートサイトとの違い
コーポレートサイトと採用サイトでは、運営目的とターゲットが違います。
コーポレートサイトのターゲットは取引先、見込み顧客や新規顧客、自社製品のユーザーなどがメインです。
コーポレートサイトではターゲットにあわせて、製品紹介や会社概要、取引実績などをメインコンテンツとします。
一方で、採用サイトのターゲットは求職者であるため、募集要項や選考フローがメインコンテンツとなります。
求職者の場合、志望企業の実績や事業内容も調べますが、企業情報以上に採用情報を求めて企業研究を行います。
採用サイトでは、コーポレートサイトだけでは知ることのできない社員の様子や社内制度など、自社を選んでもらう決め手となるような、採用に関するコンテンツを充実させましょう。
採用サイトを制作することで得られる利点
ターゲットに合わせた採用サイトを運営することは、採用成功率の向上にもつながります。
そこで、採用サイトを制作することで得られるメリットを3つ解説していきます。
1.求人サイトよりも自由さを得られる
採用サイトは、マイナビやリクナビなどの求人広告媒体に比べて、自由度が高いメリットがあります。
求人広告では写真枚数の制限や文字数の制限、原稿の大きさが決まっていることから、発信できる情報が限定されます。また、フォーマットも決まっているため、デザインなども均一です。
一方、自社で運営する採用サイトは、完全なオウンドメディア(自社所有の媒体)となるため、社内で自由に制作が行えます。文字数や写真枚数の制限はなく、新たな情報があれば日々更新ができるため、求人広告に比べて柔軟に編集ができます。
自由に制作できるからこそ、ターゲットの満足度を図るコンテンツを追求できることは、採用担当にとって大きなメリットといえるでしょう。
2.求人広告に頼らず応募を集められる
自社の採用サイトの認知度が上がりPV数をある程度確保できれば、求人広告に頼らずに採用活動が行えます。
求人広告の掲載費用は枠の大きさにもよりますが、おおよそ50~100万円ほどの価格帯が一般的です。
さらに、求人広告は一度掲載すると、原則として大幅な原稿修正や情報の更新ができません。万が一、掲載した広告の修正が必要になった場合は、変更が行えないことをデメリットに感じることでしょう。
しかし、採用サイトの場合は、自社内で制作および運営をしていれば、いつでも修正が可能です。広告費をかけず、人件費以外はほとんど無料で採用活動を行うことができます。
3.採用後のミスマッチ防止につながる
採用サイトでは、自社の情報を制限なく掲載できるため、求職者は応募前に企業の実態の細部まで確認ができます。
また、求職者は事前にしっかりと採用サイトで詳細な情報を把握した上で応募するため、ミスマッチが起こりにくく、採用後の早期退職を抑えられるメリットが挙げられます。
そのため、採用サイトを運営する場合は、会社の内情がわかるコンテンツや詳細情報の掲載が重要になります。
採用サイトを作る3つの方法
採用サイトを作成するには、主に以下のような方法があります。
社内で制作する
柔軟性が高く、最もコストが抑えられる方法は、自社内で制作から運用まで行うことです。
社内にデザイナーや「WordPress」を使用できる人材がいれば、外部委託する必要がなく、社内だけで制作ができます。外注にかかる製作費が不要です。
細かいニュアンスや表現方法なども、自分たちで作成するため完成後のサイトイメージが大きく、かい離することもありません。
ただし、社内で採用サイトを運営する場合、そのための人員確保が必ず必要となります。
外部に依頼する
社内に制作できる人材がいない場合は、外部委託することも選択肢のひとつです。
制作に関するコストは掛かりますが、デザインのプロや採用のプロに委託することで、良質な採用サイトの制作が可能になります。
また、手離れもよく、制作から保守管理まで任せることができれば、社内で採用サイト運営に人員を割く必要がないため、人員的コストを抑えられます。
ただし、サイトの制作・運営を外部に委託する場合は、事前の打ち合わせには、十分に時間をかけましょう。
成果を上げるために重要となるテキストコンテンツやデザインなど、完成後にイメージと異なる場合があるため、注意すべきポイントのひとつです。
採用管理システムを導入する
採用サイトの制作と同時に、採用管理システムの導入も検討しましょう。
また、採用管理システムの中には、応募者の情報やスケジュール管理だけではなく、採用サイトを作成できるタイプのものもあります。
採用サイトの作成から採用管理までを一連の流れで行うことで、人材採用の効率アップや生産性の向上も期待できます。
そこで、採用サイトの作成を考えている企業は、TalentClip(タレントクリップ)の導入を検討してみてはいかがでしょうか。
TalentClip(タレントクリップ)では、採用管理はもちろん、簡単なテキスト入力で、思い通りの採用サイトがつくれます。
採用サイトのページから応募者管理まで一貫して行うことで、採用活動の効率が上がるため、現場の生産性が大きく向上します。
TalentClip(タレントクリップ)の詳細に関しては、以下のURLからご確認ください。
採用サイトで掲載すべき7つのコンテンツ
採用サイトを運用し、実際に採用を成功させるためには、良質なコンテンツ制作が重要です。
採用情報はもちろん、そのほかにもオフィスの情報や社員の様子など、会社の内部事情も多く掲載するようにしましょう。
1.募集要項
新卒中途採用問わず、採用サイトに募集要項を掲載することは必須です。
必用なスキルや求める人物像など、自社にどのような人材が必要であるか、詳細に記載しましょう。
募集要項を詳細に書かないと、ミスマッチの発生や母集団の形成が上手くいかない原因となるため、注意が必要です。
また、企業に必要な人材の要件だけではなく、勤務時間や待遇、休日といった求職者が気になるポイントの記載も重要事項です。
募集要項を充実させることで、サイトに訪れた求職者に対してより多くの情報を提供できます。
2.選考プロセス
採用サイトをつくる際は、選考プロセスを記載することも忘れてはいけません。
多くの求職者が応募後の選考プロセスを気にしており、インターネットで「企業名 選考フロー」など、実際に検索する人もいます。
実際の選考プロセスを知れることは、応募者にとってメリットになります。
なぜなら、選考プロセスを記載し、具体的なスケジュール感を表すことができれば、応募後のイメージを事前に掴み、転職に向けてのスケジュールがたてやすくなるからです。
サイトに選考プロセスを掲載することで、求職者や応募者に好印象を与えるため、企業にとっても大きなメリットになります。
3.会社の事業内容
会社の事業内容は、コーポレートサイトだけではなく、採用サイトにも記載しましょう。
ただし、採用サイトはターゲットが取引先ではなく求職者になるため、記載するポイントは多少違いがあります。
採用サイトには、売上や事業の魅力ではなく「事業の目的」「将来への想い」など会社の、ビジョンや理念などに焦点をおいて記載することで、求職者が共感しやすくなります。
また、事業内容を掲載する際は、他社との差別化や自社が力を入れているポイントなどをわかりやすく記載することで、同業他社を志望している求職者の興味を引くことにもつながります。
4.社員紹介
特に力を入れたいのが社員紹介です。
求人広告では、掲載できる内容や文字数に制限があるため、なかなか詳細まで記載できません。しかし、自社の採用サイトの場合は、制限なく記載できるのがポイントです。
また、求職者の多くは、実際に働いている上司や先輩がどのような人か、非常に気にしています。
社員インタビューやクロストークなどを記載することで、採用サイトを見た人が、より入社後のイメージを持ちやすくなるため、特に社員紹介ページの充実化をおすすめします。
5.オフィスや働く環境
社員紹介と同じく、オフィス紹介も力を入れたいポイントです。
写真の撮り方などもこだわり、オフィスが働きやすい環境であることを発信しましょう。
また、静止画ばかりではなく、ビデオカメラで撮影もひとつの施策になります。撮影したビデオに、企業からのメッセージやコメントなども挿入して、求職者がオフィスツアーのような体験ができれば、非常に効果的なコンテンツのひとつになります。
6.研修/福利厚生
特に、若年層の人材や未経験者を採用する際は、研修の有無や制度を記載すると効果的です。
若年層の人材は、入社後の不安などもあり、研修制度が整っている企業に対して魅力を感じます。
また、福利厚生は新卒や中途を問わず、よく気にされるポイントのため、各種保険や退職金、有給取得率などの福利厚生も詳細に記載するのが良いでしょう。
7.よくある質問
採用活動をとおして、頻出される質問はあらかじめQ&Aとしてサイト内に記載するようにしましょう。
サイト内では、どうしても細かい部分までは含められないことがあります。しかし、疑問が残ってしまうような不十分な内容だと、情報収集が求職者の負担となったり、求職者の心が離れたりする原因にもなりかねません。
採用に関する求職者の疑問のなかには、共通してよく聞かれる話題などもあります。
そのような、よくある質問も含め多くの情報を網羅しておくことで、離脱を防いで応募までの動線を確保することにもつながります。
採用サイトを制作する際のポイント
実際に、採用サイトを制作する際は、いくつか抑えておくべきポイントがあります。
以下で述べるポイントをしっかりと意識することで、効果の高い採用サイトをつくることができます。
採用成功率を上げるため、事前に把握しておきましょう。
写真にこだわる
メンバーやオフィスを紹介するページでは、写真にこだわるようにしましょう。
求職者がサイトを見た瞬間、文章よりも全体的なビジュアルが目に留まります。
写真に力を入れてキレイに整えておくことで、求職者がサイト自体に興味を持ってくれるきっかけを作ることにもつながります。
費用はかかりますが、可能であればプロのカメラマンに依頼をし、ライティングや撮影シーンにもこだわった写真を撮ってもらうのも良いでしょう。
ターゲットに沿ったデザインにする
サイトのデザインを決める際は、自社が必要としているターゲットにあわせて作り込むようにしましょう。
ターゲットとなる人材から外れたデザインにしてしまうと、サイトに訪れたとしても早期に離脱してしまうことが考えられます。
事前に、ターゲットがどのようなデザインに興味を持つかをリサーチしておきましょう。候補者となる人材が惹かれる要素を含めることができれば、母集団形成にも効果的です。
応募への動線を考える
採用ページを作る際、こだわればこだわるほど、ページ数や内部リンクの数も多くなります。
そこで意識してほしいのが、応募への動線をきちんと確保することです。
どのページからも応募フォームにたどり着けるよう、「各ページに応募フォームへの動線」を作り込んでおきましょう。
各ページに応募への動線があることで、求職者が興味を持ったタイミングで、すぐにアクションが起こせるため、より多くの応募者を集められます。
サイトの効果測定を行う
採用サイトは作成して終わりにするのではなく、随時効果測定を行いましょう。
PV数やコンバージョンを意識し分析することで、サイトの課題点や成果が出ている部分が可視化できます。
また分析を行い、改善を繰り返すことで、日を追うごとにサイトのクオリティも上がっていきます。そのため、頻繁に効果分析を行うことが必須になります。
まとめ
採用を成功させるために、自社で採用サイトを運営することは非常に大事なことです。
まずは採用サイトとコーポレートサイトの違いや、メリットを理解し、自社に適したサイトの設計を行うようにしましょう。
そして、作成の際、重要なポイントを抑えてサイトを制作することで、最終的に採用成功率アップにつながります。ぜひ、本記事を参考にして、ターゲットが集まる採用サイトを作り上げていきましょう。